宅建の難易度と合格率は?難関資格に挑むコツ
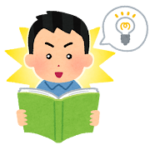
宅地建物取引士(以下、宅建)は不動産業界で重要な資格の一つであると同時に
教養としても魅力的で、毎年多くの受験者が挑戦する試験です。
しかしその合格率は例年15%から18%程度と低く、簡単な試験ではありません。
本記事では、宅建の難易度や合格率が低い理由について詳しく解説していきます。
併せて、合格を目指す際のポイントも経験者として解説していきます。
結論
合格率は気にするだけ無駄。真剣でない人も大勢いる
出題傾向が安定している試験なので過去問をやりこむ事が定石
宅建業法と法令上の制限を重点的にこなせば難しい試験ではない

振り返れば宅建って本当によくできた試験やと思うわ。
歴史があるだけに出題内容が安定してるから努力が報われやすいんやで。
宅建試験の概要を確認
宅建試験は、国土交通省が認定する国家資格試験であり、不動産取引に関する知識が問われます。
試験は毎年1回、10月に実施され、受験者数は30万人前後に及びます。
これは数ある資格でもトップ5に入る物凄い受験者数であり、屈指の人気資格とも言えますね。
試験科目は以下の5つに分かれています。
税法と免除科目を合わせて4種分別しているサイトもありますが、正確には5種分別となります。
- 権利関係 14問(民法・借地借家法・区分所有法など)
- 法令上の制限 8問(都市計画法・建築基準法など)
- 税法・その他 3問(不動産関連税制・相続など)
- 宅建業法 20問 (宅建業免許・宅建士・報酬の制限など)
- 免除科目 5問 (統計・景品表示法・地価公示など)
試験は50問の4択式で行われ、合格基準点は年によって変動しますが、例年35点前後(50点満点)と
なっています。
回答は全てマークシート方式であり、文字を書き起こす記述式問題は一切ありません。
配点は1問につき1点であり、問題内容によって点数格差はありません。
受験を志願した時点で不動産業の従業員であり、登録講習を受けている人は❺が免除されます。

出題順もこの並び通りやで。解きやすい部分から回答する事が可能や。
合格する為のコツ2点!
合格率15~18%と聞くと身構えてしまうかもしれませんね。
ですがご安心を、宅建には合格した人達が残した定石といえる攻略法が確立しています!
しっかりと確認し、活かしていきましょう。
筆者も実践し、4か月と少しで合格した攻略法でもあります。
その1 宅建業法と法令上の制限を徹底的にやりこむ
試験問題50問のうち、宅建業法と法令上の制限の2科目で28点分もの出題があります。
そしてこの2科目は前提条件の理解や知識の応用が求められる事が少なく、暗記と周辺知識が中心となる為
身に付きやすい学習科目でもあります。
この2科目、意外にも勉強量は実はそこまで多くはなく、1週するのに多くの時間は必要としません。
それにも関わらずこの出題量ですから、問題を作る側の手口は限られておりひっかけ問題対策も容易です。
宅建業法と法令上の制限でしっかり得点する事は合格する為には外せない戦法といえます。
筆者の試験結果では宅建業法20点満点、法令上の制限は7点でした。
その2 過去問の解説を理解するようにやりこむ(一例付)
独学でも資格講座でも欠かせないのが過去問。過去問を制する者は試験を制すると言えます。
しかし不合格になる人の要因は、この過去問の使い方が悪い事に起因しているケースもあります。
過去問を暗記する事に、価値はありません。
解説を理解し、知識として取り出せる事(アウトプット)に価値があります。
試験問題というのは全く同じ文体・内容で再出題される事は稀です。基本的には前提条件を変えたり数字を
変化させて受験生を惑わせるように出題されます。
国家試験というのは落とす為に作られている訳ですから、ひっかけは当然使われる手法です。
ただ単に過去問の周回だけしていると問題を暗記してしまう事も多かれ少なかれ起こります。
しかしそのような問題を、正解択だけ選んで高速周回するようになると、出題方法を捻られた際に
回答できない事や、ひっかけ問題に易々とハマってしまうという事態が頻発します。
何故この選択肢は不正解なのか?その理由を、自分で説明できる程に理解できていれば
周辺知識が身についていき、多少問題が捻られた程度で正誤を悩むことが少なくなるのです。
法令上の制限より、一例をあげておきましょう(令和5年出題)
【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ
の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市
にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に
伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造
成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定するこ
とができる。
「宅地造成工事規制区域」「造成宅地防災区域」
語感の似ている単語ですね。これはただ正解択を覚えて周回している人を引っかける絶好の要素なのか
過去問でも頻繁に見かける問題です。
この選択肢こそが×であり、正解択なのですが理由を説明できないと捻られた際に失点しかねません。
問題文が仮に区域外であれば一転して〇となります。
- 今から作ろうとする際、安全の為に規制をかける宅地造成工事規制区域内なのに
- 既に作られたココは危ないから、対策してねと宣言する造成宅地防災区域にする
こう理解して、出題者は何を言ってるんだ?と突っ込めるようになればバッチリです(笑)
市町村長からの要望があれば~等、変な前提が加わっても大丈夫ですね。

ちなみにこの1例作るだけで数十分かかってるんやで・・・

問題集作ってる人はそれだけで仕事になる位だし大変だよね
宅建の難易度が高い納得の理由
宅建試験の最大の特徴は、出題範囲が非常に広いことです。
民法などの法律知識から不動産関連の実務知識まで、多岐にわたる問題が出題されます。
その為特定の知識だけ身につければ良いというものではなく、幅広い学習が求められます。
この特定の何かだけ学べば良いと言えない点こそが勉強の負担となってきます。
人間とは不思議なもので、毛色の違う学問を学ぶのに強い抵抗を感じるのです。
くわえて暗記が中心の宅建業法と、理解・応用が中心の権利関係や税法は真逆と言える性質であり
並行してしまった多くの受験生を苦しめています。
例えば、簿記であれば日々の取引を記録した帳簿を作成し、決算書を作成する知識を身に着けます。
実際の企業経営や商品取引の手通き、税法の理論を学ぶ必要はありません。
筆者も簿記の資格は持っていますが、ほぼ計算だけというのは勉強の際に大変取り組みやすかっただけに
宅建に挑戦した際は、定石を知っていてなお随分とギャップを感じました。
少しでも負担感を減らすには
- 暗記重視の宅建業法・法令上の制限を前半に学習
- 理解、応用が中心の権利関係は後半に学習
という学習計画をお勧めします。
暗記科目と理解科目は分けて学習し、身に着けていきましょう!

暗記だけしてればいい初期はともかく、権利関係の勉強と暗記科目の復習が
重なる時期になると本当にしんどいで。

だから暗記系の宅建業法・法令上の制限をやりこむ時期と権利関係を
やりこむ時期はズラした方が良いんだね!
合格率が低い理由は難易度ではない!
では難易度が高いから合格率が低いのも仕方ないかと言われたら、そうとも言い切れません。
確かに相対評価試験(成績上位者の一定割合にのみ合格を与える)であるのは事実です。
しかしながらそもそも合格ラインにすら乗っていない受験生が大勢いるのです。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構が公表している令和6年のデータによると
| 申込者数 | 301,336人(男 194,091人、女 107,245人) うち、登録講習修了者 55,343人(男 34,380人、女 20,963人) |
| 受験者数 | 241,436人(男 154,113人、女 87,323人) うち、登録講習修了者 49,337人(男 30,517人、女 18,820人) |
| 合格者数 | 44,992人(男 27,399人、女 17,593人) うち、登録講習修了者 10,822人(男 6,201人、女 4,621人) |
となっており、合格率は18.6%(登録講習者は21.9%)となっています。
実に2割もの人は受験会場に来ていないという事です。
また、受験者約24万人全員が全力で勉強に取り組んできたとは言えない要素が多くあります。
宅建試験は受験資格が存在せず、必要勉強時間も平均的で、誰でも受験可能であるだけに
- 会社が強制的に一括で申し込んだから受験
- 時間が足りなかったけどせっかくだし受験
- 来年本腰を入れて挑むための受験体験
という受験生も少なくありません。
例えば弁護士、税理士、医者等であれば資格の有無は正に天地の差であり、己の人生の分岐点となります。
何千時間と積み上げた努力を無駄にしない為にも死力を尽くして挑む事でしょう。
実際、受験生の質も凄まじい高さです。
対して宅建士は独占業務こそあり必須業務でもありますが、不動産業界における業務全般としてみれば
限定的であり、営業活動自体は無資格者でもなんら問題なく行えます。
この「資格が無くても良い」というのは言い換えれば「気が向いたときに取ればいい」といえます。
本気で取り組む受験生とは当然差が生まれますので、受験生全員で凌ぎを競うという世界ではないですね。
つまりこの24万人の受験生全員が真剣ではなかったと言えます。
筆者はきちんと対策し、真剣に挑めば30%は超えると感じていますよ。

300時間もの勉強は本人にやる気がないと無理やからなぁ。
会社が無理やり受けさせてもお金の無駄な気がするで・・・
まとめ
宅建試験は幅広い出題範囲と学習傾向の違いから、決して簡単な試験ではありません。
しかし、適切な学習計画を立て過去問の理解を深めることで、合格の可能性は十分に高まります。
効率的な勉強を心掛け、ぜひ宅建合格を目指してください!応援していますよ!!!



